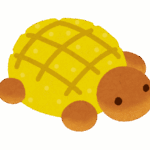はじめに:誰もが一度は疑問に思う“点滅信号”
👟「歩行者信号がチカチカし始めて、慌てて走った…」
🚦「このタイミングって、短すぎない?」
そんな経験、一度はあるのではないでしょうか。
そもそもあの点滅は何秒前から始まってるの?
誰が、どんな基準で“点滅開始の秒数”を決めてるの?
本記事では、この見落とされがちな交通ルールの裏側を、わかりやすく&深掘りして解説します!
歩行者信号のチカチカ、正式名称は?
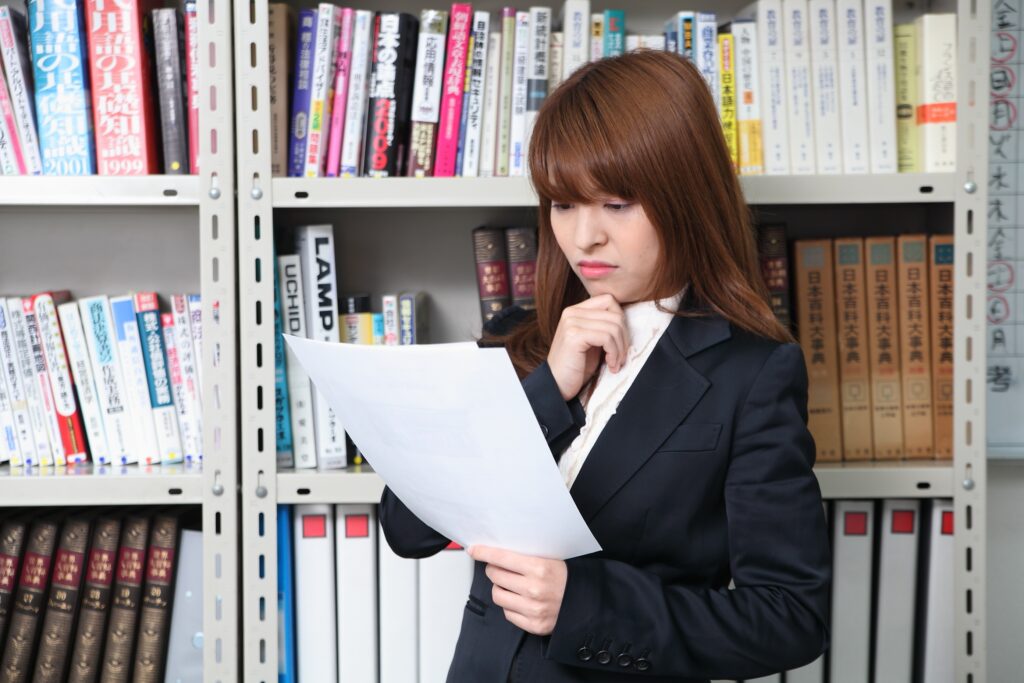
まず押さえておきたいのは、
いわゆる“チカチカ点滅”の正式な呼び方は……
🟥 「歩行者用灯器の点滅表示時間」
点滅は、「信号の切り替わり直前」であることを視覚的に警告する役割を持っています。
🚨【注意】この点滅中は「横断を開始してはいけない」と道路交通法で定められています!
あの点滅タイミング、どうやって決めているの?
ここが本題です。
結論から言うと、点滅時間の秒数は以下のような数式や基準を元に決定されています。
🚦 「道路の幅 ÷ 平均歩行速度」+ 安全マージン
例:横断歩道の幅が12m、平均歩行速度が1.0m/s → 最低12秒必要
📌 平均歩行速度は 1.0〜1.2m/秒 と想定されています。
これは高齢者や子どもでも無理なく渡れる速度として設定されています。
さらにこの秒数の**後半数秒(だいたい5秒前後)**が、
「点滅=注意喚起」として使われます。
信号の秒数を決める“根拠”とは
日本ではこの点滅時間や信号制御について、主に以下のようなルール・指針に基づいて設計されています。
| 基準書名 | 管轄 | 内容 |
|---|---|---|
| 道路交通法 | 警察庁 | 歩行者信号の点滅中の行動規制など |
| 道路構造令 | 国交省 | 歩道の幅、信号設置の基準など |
| 道路交通信号設置基準 | 都道府県警 | 信号設置の細則(歩行者用灯器の点滅時間など) |
これらをもとに、**現地の道路幅・交通量・歩行者属性(高齢者の多さなど)**を加味して、秒数が決定されているのです。
【表で比較】都市部と地方で違う秒数

都市と地方で信号の点滅時間に差があるのをご存知ですか?
| 地域 | 横断歩道の幅 | 点滅時間(平均) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 都市部(新宿・渋谷) | 8〜12m | 約5秒 | 短めだが交通量多く人も多い |
| 地方都市(岡山・熊本) | 12〜16m | 約6秒 | 高齢者を想定したやや長め |
| 高齢者配慮エリア | 8〜10m | 8〜10秒 | 歩行速度0.8m/sで計算 |
📍このように、一律ではなく地域性が反映されているのがポイントです。
誰が決めてる?信号秒数の“管轄”と“ルール”
「じゃあ実際に“信号の秒数”を決定してるのは誰?」
その答えは…
🛑 各都道府県の公安委員会(警察)が主体
具体的には:
- 現場調査(道路幅・人通り・交通量)
- 平均歩行速度の想定(0.8m/s〜1.2m/s)
- 地域の特性(高齢化率、通学路、観光地など)
これらの要素を加味して、信号制御装置にプログラムを設定しています。
🚨 つまり、“自動で全国統一”されているわけではなく、かなり手作業で細かくチューニングされているのです!
海外との違い|日本の信号は安全優先
海外と比べて、日本の信号設計は「安全第一」です。
たとえば…
| 国 | 点滅時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本 | 5〜8秒 | 地域差あり、慎重な設計 |
| アメリカ | 3〜5秒+カウントダウン | 秒数表示あり |
| フランス | 点滅なし+音声信号 | 高齢者や視覚障がい者向け整備進む |
| 台湾 | 信号が“秒数表示”+“キャラクターが走る” | ユニークなビジュアル演出あり |
🧠 海外では「秒数表示型の信号」が主流になってきており、
「あと何秒で赤になる」が可視化されていることも多いです。
まとめ:点滅の裏にある細かすぎる配慮

歩行者信号の点滅、普段は見過ごしているかもしれませんが、
その秒数の裏には驚くほど細かい計算と配慮が詰まっています。
✅この記事のまとめ
- 点滅開始は「歩行速度×道路幅」+マージンで計算
- 管轄は都道府県公安委員会(警察)
- 地域によって秒数は違う
- 日本の設計は安全第一&高齢者対応重視
- 海外は「秒数表示型」や「ユニーク演出」が進んでいる
🚦 何気ない「チカチカ」には、命を守るための科学と人間工学が詰まっているのです。
次に信号が点滅したとき、ちょっとだけ意識を向けてみてくださいね。