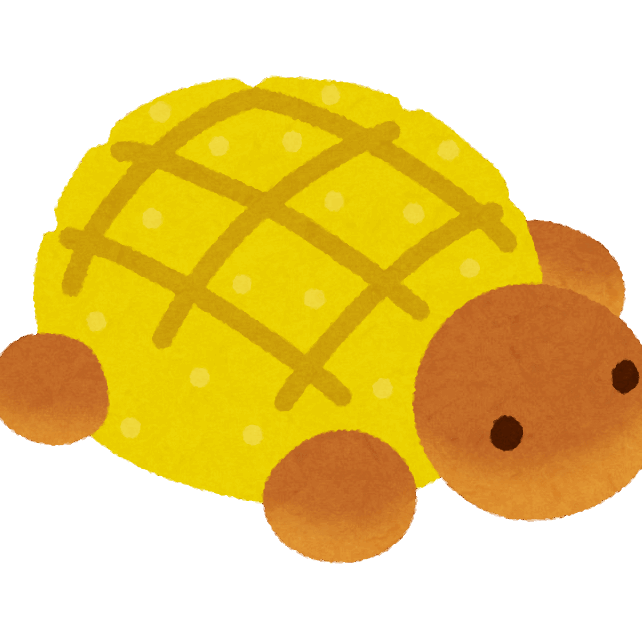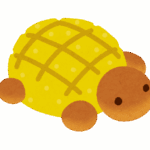なぜ「序論」が重要なのか

序論は、**読者にとっての「入口」**であり、
論文全体の第一印象を決める超重要パートです。
📌こんな役割があります:
- この研究がなぜ必要かを示す
- テーマの背景や目的を伝える
- 本論への導線をつくる
💬指導教員が最も目を光らせて読む部分でもあるので、手を抜けません…!
序論で書くべき5つの要素
以下の5要素を盛り込むことで、**「型に沿った安心できる序論」**が完成します👇
① 問題意識(導入)
📍「なぜこのテーマを扱うのか?」という動機や社会的関心を示します。
例:
現代社会において、○○という課題が注目されている。特に若者を中心に△△という現象が広がっている。
➡️ 読者の共感や関心を引き出すきっかけに!
② 先行研究の紹介
📚既に研究されている内容を簡潔に紹介し、
自分の研究の立ち位置を示します。
例:
○○については、▲▲(2020)や□□(2022)が詳細に論じている。
➡️ 「自分の研究がどこから出発しているのか」が分かるように
③ 研究の目的・問い
🔍「本研究で何を明らかにしたいのか」を明確に書きます。
例:
本研究では、○○における△△の表象を分析し、□□との関係性を考察することを目的とする。
➡️ 目的が曖昧だと、論文全体がブレます!
④ 使用する資料・方法
📖 文献、インタビュー、作品、アンケートなど、分析対象や方法を簡単に紹介します。
例:
本研究では、A作品およびB作品を分析対象とし、比較表象論の手法を用いて検討する。
➡️ 本論に入る前の「手がかり」を与えることが重要
⑤ 本論の構成予告
📑 「この後どう展開するのか」を軽く伝えます。
例:
第1章では〜、第2章では〜、最終章では〜を論じる。
➡️ 読者にとって「地図」の役割を果たします🗺️
魅力的な書き出しテクニック3選
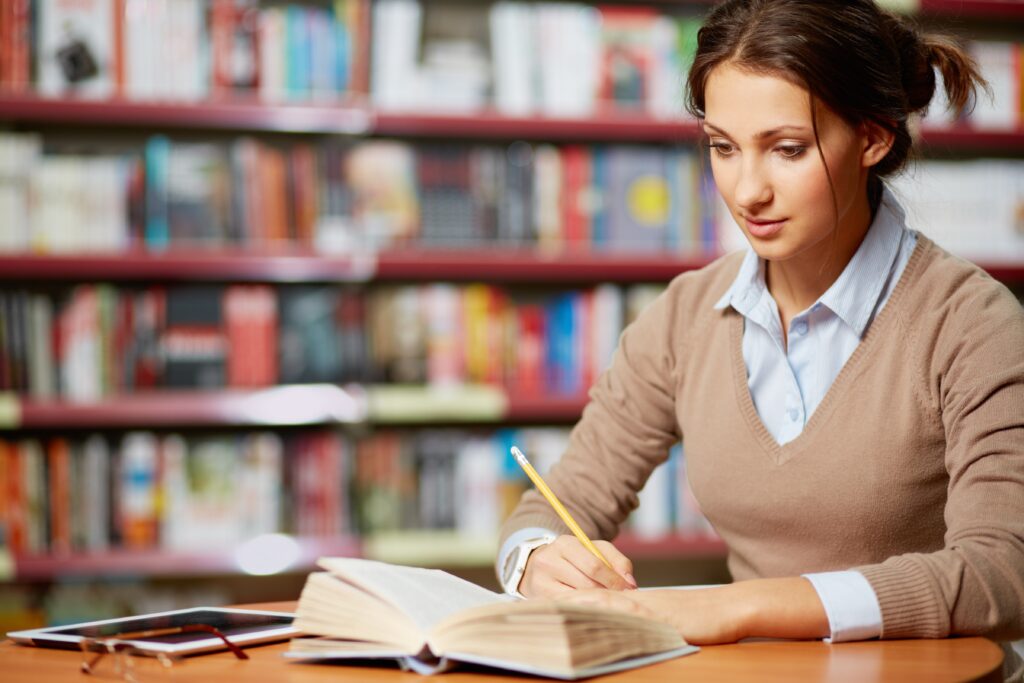
🎯テク①:具体的な事例から始める
→ 抽象的な説明よりも、「ニュース」や「身近な話題」から入ると読者が引き込まれやすい!
例:
2024年、SNS上で「○○現象」が話題を呼んだ。この現象は〜
🎯テク②:疑問形で問いかける
→ 問いから始めると、「このあと答えてくれるんだな」と読者に期待感を与えられます。
例:
なぜ人々は○○を美しいと感じるのだろうか?
🎯テク③:印象的な引用で始める
→ 有名な言葉や作品からの引用は説得力と知的印象を与えてくれます。
例:
「人は物語によって生きている」──ジェローム・ブルナーのこの言葉は…
📝注意:引用は出典明記が必須です!
NG例と改善例で学ぶ!序論の改善ポイント

❌NG例
私は○○というテーマに興味がある。だからこのテーマで卒論を書こうと思った。
👎【問題点】
・個人的すぎる
・論理的な流れがない
・「研究」になっていない
✅改善例
近年、○○という社会現象が顕著に現れている。これに関して、××や△△といった研究は行われてきたが、□□に注目した分析は少ない。そこで本研究では、〜を目的として、〜という方法で考察を行う。
👍【改善ポイント】
・問題提起→先行研究→研究目的→方法へと自然に流れている
・客観的で論文らしいトーン
よくある質問Q&A
❓ 序論って最初に書いた方がいいの?
➡️ YesでもありNoでもあり。
- 構成案や章立てが決まっていれば先に書いてもOK
- ただし、本論を書いた後にブラッシュアップする人も多いです🛠️
❓ 序論に「主張」は書いていいの?
➡️ 簡潔に触れるのはOK。
ただし、本格的な論証は本論で展開するのが鉄則です。
❓ どれくらいの分量が適切?
➡️ 全体の15〜20%程度が目安(例:1万字の卒論で1500〜2000字)
まとめ:序論は読者への「プレゼン」!

🎤 序論はただの導入文ではありません。
それは 「この研究には価値がある!」と伝えるプレゼンです。
✅ 読者の関心を引く冒頭
✅ 論点と目的の明確化
✅ 読み進めたくなる構成案内
を意識すれば、説得力ある序論が完成します!
📌 次回予告:「結論パートの書き方完全解説!卒論の締め方で差をつけろ🖋️」