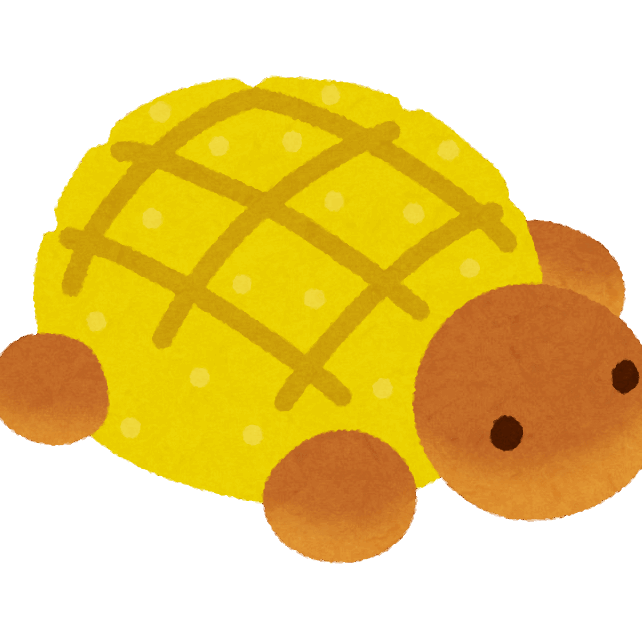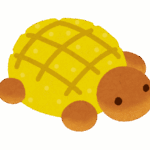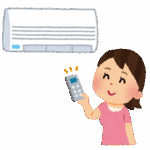🏗️卒論の構成案テンプレート&書き方完全解説!序論・本論・結論の中身を迷わない!
はじめに:なぜ構成が大事なのか

卒論の悩みで最も多いのが…
「何から書けばいいのか分からない😱」
というもの。
でも安心してください。
書き始める前にしっかり構成案(アウトライン)を立てておけば、
- 何を書くか明確になる
- 論理の流れが整理できる
- 書く作業がラクになる
と、いいこと尽くしなんです✨
卒論の基本構成「序論・本論・結論」とは?
🎓多くの卒論は、以下のような3部構成が基本です:
| 部位 | 内容 | 分量の目安(1万字の場合) |
|---|---|---|
| 序論 | 問題提起・背景・目的など | 約1500〜2000字 |
| 本論 | 分析・議論・実証 | 約6000〜7000字 |
| 結論 | 結果のまとめ・課題・展望 | 約1000〜1500字 |
💡POINT:
- 章立ては3〜5章が一般的(多すぎると散漫になる)
- 論点ごとに1章ずつ展開するのが理想的
🔧構成案テンプレート:章ごとの見本例
ここでは、文系卒論の一般的な構成案のテンプレートを示します。
markdownコピーする編集する【タイトル案】
「○○にみる××の変遷──△△を通して読み解く現代社会」
【構成案】
第1章 序論
・テーマ選定の背景
・問題意識と研究目的
・先行研究の紹介と本研究の位置づけ
・使用する資料・方法の説明
第2章 ○○の理論的枠組み
・○○とは何か
・××における理論の展開
第3章 △△における○○の分析
・具体的事例分析①
・具体的事例分析②
第4章 考察
・事例から見える傾向
・理論との照合と議論
第5章 結論
・全体のまとめ
・研究の意義と今後の課題
📌この構成案はそのまま提出フォーマットにも流用できます!
章ごとの書き方ポイント
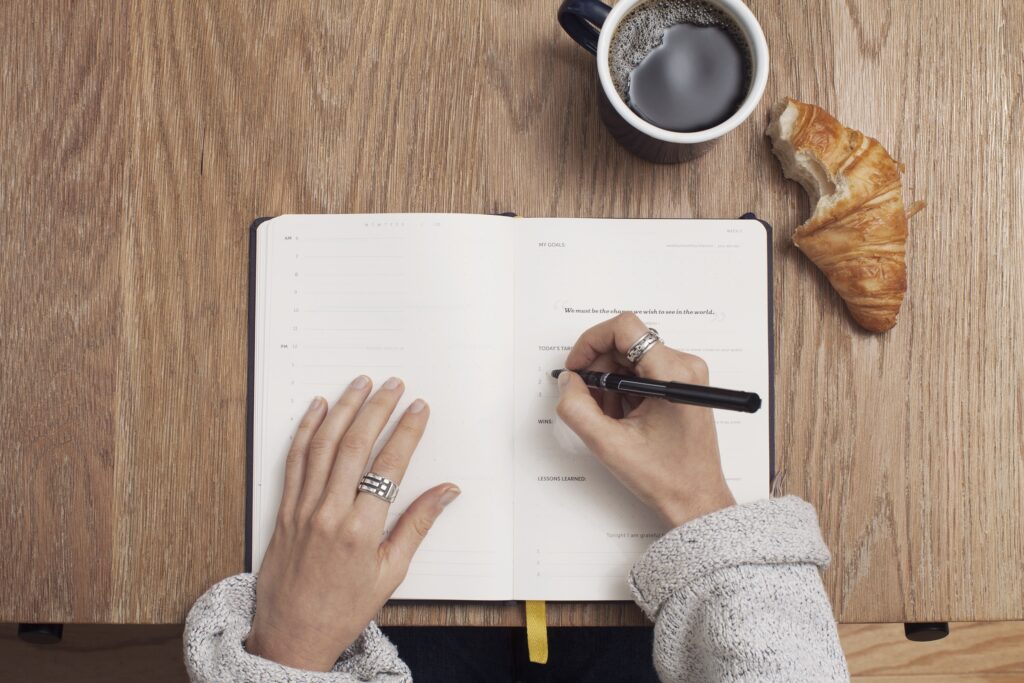
🎯序論:問い・背景・目的を書く
序論は読者に「この研究は必要だ」と納得させるパートです。
✅書くべき内容は以下の通り:
- 研究の背景・問題意識(なぜこのテーマを扱うのか)
- 研究目的・問い(何を明らかにしたいのか)
- 先行研究と本研究の位置づけ(新規性・独自性)
- 方法論・資料紹介(何をどう使って分析するか)
💡 POINT:
最後に**「本論で何を論じるか」**という構成予告を書くと読みやすくなります!
📊本論:複数章に分けて展開
本論は卒論の核!分析や議論を掘り下げましょう。
章の立て方のヒント:
- 第2章:理論や背景の整理
- 第3章以降:具体的事例や資料の分析
- 第4章:考察・議論・反証
📎注意点:
- 章ごとに主張を1つに絞る
- 章のつながり(前章のまとめ・次章の導入)も意識
🧩結論:まとめと考察
「この研究で何が分かったのか?」を明確に示すパートです。
✅入れるべき内容:
- 研究のまとめ
- 研究の意義
- 残された課題・今後の展望
📌注意:
新しい分析や議論はここでは入れないように!
よくある構成パターン3選
📘ケース①:文学作品分析
markdownコピーする編集する第1章 序論
第2章 作者と時代背景の整理
第3章 作品Aの分析
第4章 作品Bとの比較
第5章 結論
📰ケース②:メディア表象研究
markdownコピーする編集する第1章 序論
第2章 表象理論の整理
第3章 CM・広告の分析
第4章 消費者意識との関連考察
第5章 結論
🧑🎓ケース③:教育・社会系論文
markdownコピーする編集する第1章 序論
第2章 教育制度の変遷と課題
第3章 現場調査・アンケート分析
第4章 政策提言・比較分析
第5章 結論
🎯 構成は「問い」に合わせて柔軟に設計すべし!
構成案の提出時に注意すべきこと

- 章タイトルには具体性を持たせる
- ❌「考察」「分析」だけでは弱い
- ✅「第3章 A作品における親子関係の象徴的描写」
- 分量バランスを意識する
- 序論・本論・結論の割合が偏らないように
- 指導教員の指摘には柔軟に対応する
- 「第2章と3章を逆にすべき」などのアドバイスは真摯に受け止める
📢 構成案の段階でたくさんフィードバックをもらうのが成功の秘訣!
まとめ:構成は卒論の「設計図」!

✅ 構成案がしっかりしていれば、執筆はスムーズ!
✅ 章ごとの目的を意識して書き分けることが重要
✅ 書きながら構成を微調整する柔軟性も忘れずに
📝 卒論は長く見えて、実は「構成を分割すれば小さな文章の積み重ね」!
コツコツと、「書けるところから書く」ためにも、最初の構成案が鍵🔑となります!
📌 次回予告:
「序論の書き方徹底解説!読者を惹きつける導入文のテクニック」をお届け予定📖🔥