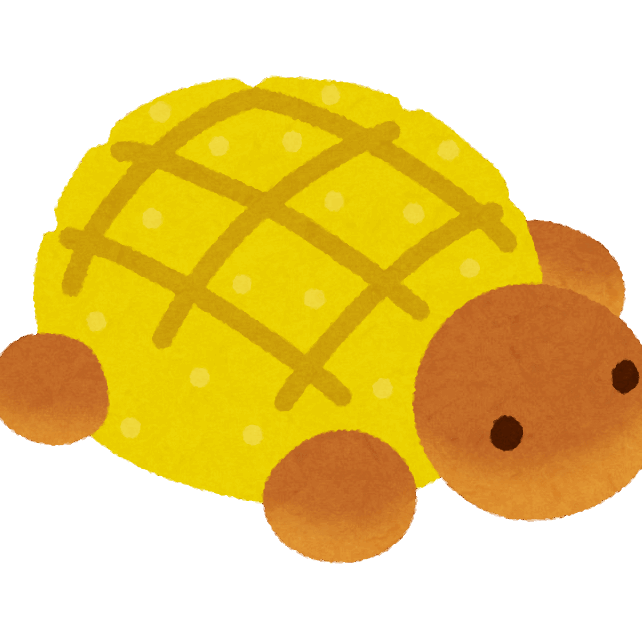⏰卒論スケジュールの立て方完全ガイド!逆算で焦らない進め方とは?
はじめに:卒論はスケジュールが9割

卒論の一番の敵、それは「時間切れ」です。
「気がついたら提出直前!」「今さら何を書けばいいか分からない…」という状況にならないためには、早めのスケジュール管理が命です。
🌟 このガイドでは:
- 卒論の逆算スケジュールの立て方
- 各時期にやるべきこと
- おすすめ管理ツール&リカバリー方法
を、具体例を交えながら解説します📅✨
まずは全体スケジュールを逆算しよう
卒論提出は通常、1月中旬〜2月上旬が多いです。
ここをゴール地点とし、以下のように逆算していきましょう。
🗓️ 卒論スケジュール全体像(文系・約1年の場合)
| 月 | 主な作業 |
|---|---|
| 4〜6月 | テーマ決定・指導教員と相談 |
| 6〜8月 | 先行研究調査・文献探し |
| 9〜10月 | 構成案作成・アウトライン固め |
| 10〜12月 | 本文執筆・部分提出・修正 |
| 12月〜1月 | 推敲・最終提出準備 |
🎯 POINT:
- ゴール(提出日)から逆算するのが基本
- 締切が複数ある(中間報告・仮提出など)場合は、小さな締切もマイルストーンに設定
具体的なステップ別スケジュール

① テーマ決定(4〜6月)
🔍 やること
- 興味のある分野を洗い出す
- 指導教員に仮テーマを相談
- 研究可能性を確認(資料があるか・スケールが適切か)
💡 Tips
- 迷ったら、過去の卒論タイトルを見て参考にしよう
- 指導教員に相談することで、早期修正も可能に!
② 先行研究調査(6〜8月)
📚 やること
- CiNii・国会図書館・大学図書館OPACで文献を収集
- 参考文献カードやノートに要点をメモ
- 重要な先行研究は本文で引用・批判できるように整理
💡 Tips
- 夏休みは文献読みのゴールデンタイム!
- ZoteroやNotionなどを使って**文献整理を「見える化」**しよう
③ 執筆準備・構成案作成(9〜10月)
🧱 やること
- 論文構成(序論・本論・結論)をざっくり作る
- 各章に何を書くか、段落ごとにメモする
- 指導教員に構成を提出し、フィードバックをもらう
💡 Tips
- この時期に構成を固めておくと、執筆が驚くほどラクになります。
- フィードバック後は「書き直し時間」も確保しておこう
④ 執筆(10〜12月)
✍️ やること
- 序論→本論→結論の順に執筆(順不同でも可)
- こまめに進捗報告を出す(前回記事テンプレ参照✨)
- 文章表現をブラッシュアップ(誤字脱字の修正など)
💡 Tips
- 書けない章はスキップして、書けるところから埋めよう
- 1章を3〜4週間ペースで書けば、12月には完成も夢じゃない!
⑤ 推敲・提出準備(12月〜1月)
📄 やること
- 印刷・製本の指定を確認(大学によって異なる)
- 図表や脚注の整理・整形
- 指導教員の最終チェックを受ける
💡 Tips
- PDF保存・USBバックアップを忘れずに
- 複数回プリントアウトして、目視で読み直すのが鉄則!
おすすめの管理ツール3選
✅ Google カレンダー
- 長期スケジュールを月単位で管理
- 提出日・相談日・執筆目標などを可視化
✅ Trello(トレロ)
- カード式で「やること・進行中・完了」が一目で分かる
- ガントチャート機能もあり!
✅ Notion
- 文献管理・構成案・TODO・メモが一括で管理可能
- 執筆そのものもNotionで進められる💡
🎯 POINT:
どのツールを使うかよりも、「自分に合った管理法を続けること」が最も大切です。
スケジュールが崩れたときの対処法
焦らない。まずリスケジュール!
「もう無理…」と思ったら、現実的な再スケジュールを。
- どこが遅れているか、原因を洗い出す
- 本当に必要な作業と省ける作業を区別
- 週単位でマイルストーンを立て直す
指導教員に早めに相談しよう
- 遅れを正直に伝え、どうリカバリーすべきか相談
- 多くの先生は、誠実な報告に対しては協力的です!
🆘 ここが重要!
「間に合いません」より、「ここまでは終わっています」と言える報告を!
まとめ:卒論成功のカギは「見える化」と「柔軟性」

✅ スケジュール管理は、卒論の不安を減らす最大の武器!
✅ 「逆算」と「分割」で、書くハードルを下げよう
✅ ツールを駆使して、「見える化」すれば継続できる
✅ 崩れたときは柔軟に立て直せばOK!
🎓 卒論は一人で走り抜けるマラソン。
でも、スケジュールという地図があれば、迷わず・焦らず・最後まで走りきれます!
📢 次回予告:
「卒論の構成案テンプレート&書き方完全解説」を予定中!
「序論で何を書く?本論は何章に分ける?」という悩みに答えます✍️📘