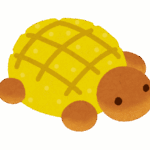はじめに:修士論文とは何か
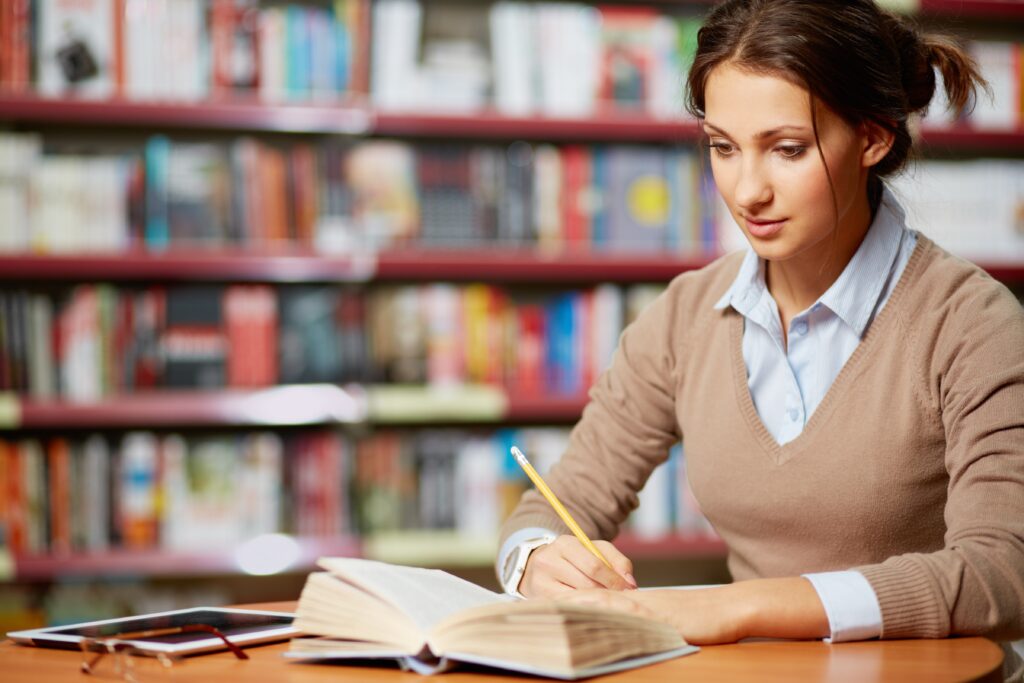
修士論文は、大学院修士課程の集大成として提出される、学術的な研究成果です。単なるレポートとは異なり、オリジナリティと論理性が問われます。
🔍 ポイント:
・研究の新規性があるか
・先行研究との関係性を明確にしているか
・論理的に一貫しているか
修論を書くことは、思考力・構築力・表現力の訓練でもあります。
テーマ設定:研究のスタート地点
🔑 テーマ決めのコツ
- 関心のあることから始める
- 資料・方法・時間など研究可能性を確認
- 先行研究の隙間を見つける
🎯 良いテーマの例(文学研究の場合)
- 「近代日本文学における父性の変容」
- 「村上春樹作品における“喪失”の物語構造」
重要: テーマは単なるジャンルではなく、問いであるべきです。例:「この作家の作品はなぜ今なお読まれ続けているのか?」
先行研究の探し方と読み方
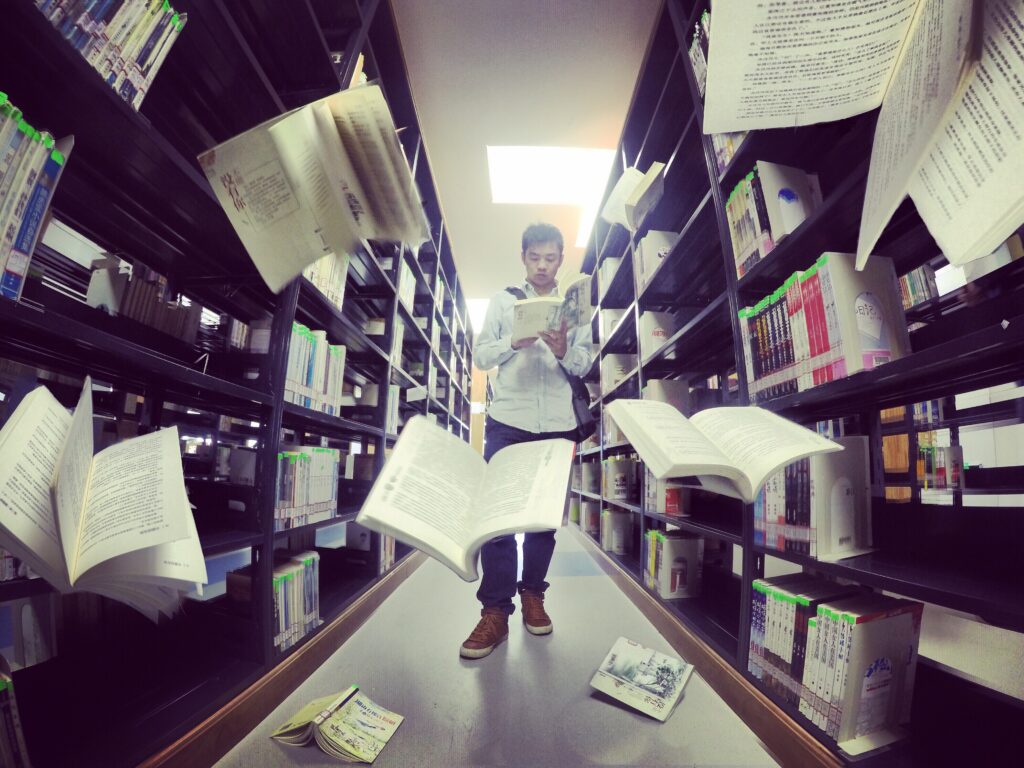
🔎 文献の探し方
- CiNii ArticlesやNDL(国会図書館)OPAC
- 大学図書館のオンラインリソース
- 指導教員やゼミの推薦文献から引用の連鎖をたどる
💡先行研究は「自分の問い」の足場であり、乗り越えるべき壁でもある。
📘 読み方のポイント
- 問いと主張を見抜く
- 方法と資料の扱いに注目
- 批判的に読む(どこに議論の余地があるか)
構成の立て方と論の展開
📐 構成の基本型(文系)
- 序章:問題提起と研究目的
- 第一章:先行研究の整理
- 第二章以降:分析・検討
- 終章:まとめと今後の課題
コツ: 各章に「問い」と「答え」を配置し、読者にとって自然に感じられる構成を心がけましょう。
🔧 論の展開で意識すべきこと
- 段階的に深める(螺旋型構造)
- 資料と主張の往復
- 引用と分析のバランスをとる
文章表現のコツと学術的な書き方
✍️ 基本スタイル
- 「である調」で統一
- 主語と述語の対応を正確に
- 無駄な修飾語は削る
💡 読みやすくする技術
- 一文は40〜50字以内を意識
- 段落ごとに主張を一つ
- 接続詞で論の流れを明示
🧩「正しい言葉」を選ぶことは、正確に考えることと同義。
引用・注・参考文献の正しい扱い
📚 引用の種類
- 直接引用:「 」で囲んで出典を記す
- 間接引用:言い換え・要約+出典明記
📌 注の使い方
- 補足情報や異論提示に使う
- 本文とのバランスを考える
📖 参考文献の整え方
- 一貫した書式で記載
- 著者名・出版年・書名・出版社を明記
スケジュール管理と執筆の実践

🗓️ モデルスケジュール(半年間)
| 月 | 作業内容 |
|---|---|
| 4〜5月 | テーマ決定・資料収集 |
| 6〜7月 | 先行研究整理・構成案作成 |
| 8〜10月 | 本文執筆(各章ごと) |
| 11月 | 全体の推敲・注・参考文献整理 |
| 12月 | 最終提出・確認 |
⏰「スケジュール通りに進まない前提で、余裕をもって計画を立てよう」
提出前のチェックポイント
- タイトルと内容の一致
- 引用・参考文献の整合性
- 誤字脱字のチェック(音読・印刷)
- 章立てや見出しの明確さ
- 指導教員のコメント反映
おわりに:論文執筆を通じて得られるもの
修士論文は、思考と表現の集大成です。大変ではありますが、その分得られるものも大きいのです。
🌱 あなたの問いは、きっと誰かの問いにも通じています。
だからこそ、書く意味があるのです。