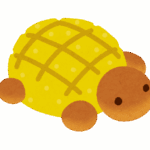1. はじめに:研究の第一歩は「文献探し」から

大学で卒業論文(卒論)、大学院での修士論文(修論)や博士論文(博論)を書くうえで、多くの学生がつまずくのが「参考文献」の探し方です。
「テーマは何となく決まったけれど、どうやって資料を集めたらいいのかわからない」
「とりあえずGoogle検索して出てきたページを読んでいるけど、これでいいのだろうか」
そんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
しかし、論文執筆において参考文献の質と量は、研究の深みを決定づける核心部分です。良い文献を探し出し、適切に読み解き、研究に生かす力=リサーチ力が高ければ、テーマの説得力が格段に増します。そしてそれは、あなた自身の研究者としての成長にも直結するのです。
このブログ記事では、文学・社会学・人文学などの文系研究を中心に、実際の論文執筆で役立つ文献の探し方・活かし方を体系的に解説していきます。記事を読み進めるうちに、あなたの「リサーチ力」が着実にステップアップすることを目指しています。
このガイドの対象読者
- 初めて卒論に取り組む学部生
- 修士課程で専門研究を深めたい大学院生
- 博論執筆に向けて研究基盤を固めたい博士課程の方
- 文献の探し方に苦手意識がある全ての研究者志望者
このガイドを読むことで得られること
- テーマに合った参考文献の探し方がわかる
- 各種データベースや図書館の活用法を習得できる
- 質の高い文献を見極める力がつく
- 読んだ文献を論文で活かす方法がわかる
2. 文献探しの心構えと研究テーマの固め方
参考文献を探し始める前に、まず必要なのは**「何を調べたいか」をはっきりさせること**です。
当たり前に聞こえるかもしれませんが、ここが曖昧なままでは、どれだけ優れた検索スキルを持っていても、ピントの合った文献にたどり着けません。
2-1. テーマ設定は「問い」から始まる
研究テーマは単なる「興味」や「好き」から出発しても構いません。
しかし、そのままでは「レポート」になってしまうことが多く、論文としての深みが出ません。
そこで必要なのが、以下の問いを自分に投げかけることです:
- なぜ私はこのテーマに関心をもったのか?
- このテーマにおいて、世間では何が常識とされているのか?
- その常識に対して、自分はどんな違和感や疑問を持っているのか?
- 私の問いに対して、どのような先行研究があるか?
これらの問いに答えることで、テーマは「好きなこと」から「探究すべき課題」へと昇華します。
そしてそれこそが、文献調査の出発点となります。
2-2. 研究テーマの3つの絞り込みステップ
文献探しに入る前の準備として、次の3ステップでテーマを絞り込むことをおすすめします。
ステップ①:広い関心領域をリストアップする
まずは漠然とした関心で構いません。以下のように、箇条書きで10個程度書き出してみましょう。
例:
- 子どもと教育
- 戦争と文学
- ジェンダーと神話
- デジタル社会と記憶
- 宗教と死生観
- 近代日本の家族制度
- 記号論とマンガ
- 動物と人間の関係
- 病と語り
- 民話と現代文学
ステップ②:「切り口」を加える
次に、先ほどの関心に対して、「誰が」「どこで」「いつ」「どうやって」などの視点を加えていきます。
例:「ジェンダーと神話」→「北欧神話における女性像の変遷」「神話における母の表象とフェミニズム批評」
この段階で、検索キーワードの候補もかなり明確になります。
ステップ③:仮のリサーチクエスチョンを立てる
最終的には、以下のような「問い」の形に落とし込むと、文献探しがぐっと楽になります。
- なぜ○○は××と描かれるのか?
- ○○という現象は、△△の観点からどう説明できるのか?
- 先行研究では□□とされてきたが、実際にはどうか?
この「問い」こそが、あなたの研究の軸となるのです。
2-3. 文献探しの心構え:正解を探すのではなく、議論の地図を作る
文献を探すとき、多くの人は「正解」を探してしまいがちです。
でも、学術研究は「正しい答えを見つけること」ではなく、**「問いに対する多様な視点を理解し、自分の立場を築いていくプロセス」**です。
つまり、文献を探す作業とは、
- 何がすでに語られてきたのかを知ること
- どこに議論の空白があるのかを見極めること
- そこに自分の研究を位置づけること
――なのです。
このように、「テーマを深めるために文献を探す」という姿勢をもつことで、作業は一気に意義のある知的冒険になります。
3. 使える情報源の種類と特徴:図書館・データベース・論文検索サイト

文献探しの質を高めるには、正しい情報源を使いこなすことが何より重要です。ここでは、大学生・大学院生にとって特に有用なリソースを、以下のカテゴリに分けて紹介します。
3-1. 図書館(大学図書館・国立国会図書館)
■ 大学図書館(附属図書館)
まず最初に頼るべきは、自分の大学の附属図書館です。ここには、学生の研究に合わせた専門書・学術雑誌・データベースが揃っています。
- **蔵書検索(OPAC)**で学内の本や論文が検索可能
- 他大学からの**文献取り寄せ(ILL)**も活用できる
たとえば:
- 東京大学附属図書館 OPAC
https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ - 京都大学図書館機構
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
■ 国立国会図書館(NDL)
あらゆる出版物を網羅する日本最大の図書館。すべての日本国内刊行資料(書籍・雑誌・論文など)を収蔵しており、リモートでも使えます。
- NDLオンライン(蔵書検索・複写申込)
https://ndlonline.ndl.go.jp/ - リサーチ・ナビ(分野別ガイド)
https://rnavi.ndl.go.jp/
→ 分野ごとに調査方法やデータベースが解説されており、超便利です。
3-2. 日本語論文・文献のデータベース
■ CiNii Research(サイニィ・リサーチ)
日本の論文検索と言えばこれ。国立情報学研究所が運営する、日本最大級の論文検索サービスです。
- 学術論文、紀要、博士論文などを横断的に検索可能
- 一部は無料で全文閲覧可能、図書館連携で取り寄せも可能
■ 国文学研究資料館「国文研データセット」
近代文学・古典文学・演劇・絵巻など、日本文学系研究者にとっては宝の山。
▶︎ https://www.nijl.ac.jp/pages/database/
■ ジャパンナレッジ(JapanKnowledge)
- 『日本国語大辞典』『国史大辞典』『人物叢書』など信頼度の高い辞書・事典を横断検索できる
- 大学からのアクセスが必要(個人契約は不可)
▶︎ https://japanknowledge.com/
3-3. 海外文献・学術ジャーナルのプラットフォーム
■ JSTOR(ジェイストア)
- 人文・社会科学の海外論文が網羅されたデジタルアーカイブ
- 大学からのアクセスが必要(リモートVPN対応あり)
■ Google Scholar(グーグルスカラー)
- 世界中の学術論文を無料で横断検索可能
- 論文の引用数・PDFへのリンクなどが一目でわかる
▶︎ https://scholar.google.com/
■ Project MUSE(プロジェクト・ミューズ)
- アメリカの大学出版会による人文社会系ジャーナルが多く収録されている
- 比較文学・文化研究に強い
3-4. 辞書・事典・年表などの基礎情報リソース
■ Web版日本大百科全書(ニッポニカ)
- 学術的な内容を平易に解説してくれる信頼性の高い百科事典
- 多くの大学図書館が契約中(JapanKnowledge経由で利用可能)
■ 日本歴史年表(国史大辞典)
- 歴史研究・時代背景を押さえたいときの補助ツールに最適
3-5. その他の便利なツール・リソース
- RESEARCHMAP(研究者情報データベース)
日本の研究者の業績・所属・研究キーワードなどがわかる
▶︎ https://researchmap.jp/ - WorldCat(世界の蔵書を探す)
グローバルな図書館ネットワークで、所在を確認できる
▶︎ https://www.worldcat.org/
3-6. 情報源を選ぶ基準
| 情報源 | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 大学図書館 | 学内で手に入る資料 | 基礎文献や所蔵確認 |
| 国立国会図書館 | 国内刊行物を網羅 | 日本語の網羅的文献探し |
| CiNii | 日本語論文の検索 | 先行研究の調査 |
| JSTOR/Project MUSE | 海外論文 | 比較研究・理論導入 |
| Google Scholar | 全体検索 | 横断的な論文探索 |
| JapanKnowledge | 事典・辞書 | 用語定義・人物解説 |
4. 文献調査の基本ステップ(『フランケンシュタイン』研究の場合)
4-1. 文献調査とは何か?
文献調査とは、既に発表されている研究成果(論文・書籍・レビューなど)を収集し、分析するプロセスのことです。
卒論・修論・博論などのアカデミックな論文では、「先行研究を参照して自分の立場を明確にする」ことが極めて重要です。
4-2. 文献調査の目的
- 既存研究の把握:自分の研究テーマがどのように扱われてきたかを知る
- 研究の独自性を明確にする:他者の視点と差別化するポイントを見つける
- 研究の理論的枠組みを支える:分析に必要な概念・理論を参照する
4-3. 文献調査の基本ステップ
✅ ステップ① テーマを明確にする
たとえば以下のような仮テーマを考えます:
「メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』における死生観と倫理の表象」
この場合、中心となるキーワードは次の通りです:
- フランケンシュタイン(Frankenstein)
- 死生観(views of life and death)
- 倫理(ethics)
- 創造/生命の創出(creation, bioethics)
✅ ステップ② キーワードを展開する
類語や関連語をリストアップして、検索の幅を広げます。
| 日本語 | 英語(翻訳キーワード) |
|---|---|
| フランケンシュタイン | Frankenstein, Mary Shelley |
| 死生観 | death and life, mortality, the value of life |
| 倫理 | ethics, responsibility, moral philosophy |
| 創造 | creation, artificial life, reanimation |
✅ ステップ③ データベースで検索する
主に使用するデータベース:
| 種類 | データベース名 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 国内 | CiNii Research | 日本語の先行研究 |
| 国内 | NDL Online | 図書・雑誌の所蔵確認 |
| 海外 | Google Scholar | 海外論文検索(英語) |
| 海外 | JSTOR、Project MUSE など | 学術雑誌の論文検索(大学契約が必要な場合あり) |
✅ ステップ④ 関連文献の収集と整理
収集した文献はExcelやZotero、Notionなどで管理すると便利です。
以下のように分類することで、論文執筆時にスムーズに活用できます。
| 分類 | 目的 | 例 |
|---|---|---|
| 直接関連研究 | 自分のテーマに直結する | 「『フランケンシュタイン』における創造と責任の倫理」 |
| 間接関連研究 | テーマと理論的に関係する | 「ロマン主義と死生観」「バイオエシックスの文学的表象」 |
| 理論枠組み | 思想・理論・方法論 | フーコー『生政治の誕生』、ハラウェイ『サイボーグ宣言』 |
✅ ステップ⑤ 文献の読み込みと評価
重要な文献を見つけたら、以下の観点から読解・メモを取りましょう:
- 研究の問いは何か?
- 扱われている資料(作品やエピソード)は何か?
- 使用されている理論・視点は何か?
- 自分の研究とどう関係するか?
✅ ステップ⑥ 再検索・深掘り
1本の論文を読み込むと、参考文献リストからさらに有用な文献を探すことができます(いわゆる「芋づる式」検索)。
また、自分の研究テーマが深まってきた段階で、新たなキーワードで再検索するのも重要です。
4-4. 文献調査は“探す・読む・考える”の繰り返し
文献調査は一度やって終わるものではなく、研究の進行とともに繰り返すプロセスです。
- 研究構想の段階で文献調査 → テーマを明確化
- 執筆中も新たな文献を発見・引用して議論を補強
- 結論を導くために理論的視野をさらに広げる
✅ この章のまとめ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① テーマ設定 | 研究テーマに合ったキーワードを整理する |
| ② 検索準備 | 類語・翻訳語をリストアップして検索の幅を広げる |
| ③ 検索実行 | データベースを使って日本語・英語の文献を調査 |
| ④ 整理・管理 | 文献を用途別に整理し、引用管理ツールに記録 |
| ⑤ 読解・評価 | 論点・資料・理論をチェックしながら読む |
| ⑥ 再検索 | 文献から新たなキーワードを得てさらに深掘り |
5. 研究テーマに合った文献の見極め方(『フランケンシュタイン』研究を例に)

「とりあえず検索してみたけど、どの文献が“使える”のかわからない…」という悩みは、文献調査のあるあるです。ここでは、『フランケンシュタイン』を研究対象とする場合に、どのように文献を見極めていくか、具体的な視点と判断基準を解説します。
5-1. 研究の軸を意識する
まず、**自分の研究の軸(=問い・視点・方法)**を常に意識してください。
たとえば、以下のような研究テーマを仮定してみましょう:
テーマ例:『フランケンシュタイン』における「死」の表象と倫理的葛藤の構造
このテーマに対して、「登場人物の死生観」「ヴィクターとクリーチャーの倫理観の対比」「科学と宗教の衝突」などが考察対象になります。
5-2. 使える文献/使いにくい文献の見分け方
✅ 【使える文献】の特徴:
| 視点 | 内容例 |
|---|---|
| 主題が近い | 「フランケンシュタインにおける死の恐怖と復活の欲望」 |
| 視点が鋭い | 「創造者責任という倫理的問題をどう描いたか」 |
| 理論が明確 | フーコーの生政治やアガンベンの「生の剥奪」を援用している |
| 原典読解が丁寧 | 作品の記述や構造を深く読み込んでいる |
❌ 【使いにくい文献】の特徴:
| 視点 | 内容例 |
|---|---|
| 要約中心 | あらすじやキャラ紹介に終始している |
| 一般論的 | 「有名な作品だから今も読まれている」などのざっくり論 |
| テーマが遠い | 「19世紀のイギリス女性作家の社会的地位」など直接関係しないもの(背景知識としては可) |
| 論拠が弱い | 引用・脚注が少なく、主観的印象で語られているもの |
5-3. 文献の「引用可能性」を判断する
学術論文で使う文献は、信頼性が高く、引用に耐える必要があります。
📌 引用に適した文献のチェックリスト:
- □ 査読付きの論文(大学紀要、学会誌など)
- □ 信頼ある出版社の単行書(例:岩波書店、ミネルヴァ書房、Palgrave など)
- □ 理論・研究動向をふまえている
- □ 参考文献・脚注が充実している
- □ 主張と根拠(テキスト引用や理論参照)が明示的
5-4. 海外論文を活用する際のヒント
『フランケンシュタイン』は海外でも膨大な研究が蓄積されています。たとえば:
- Anne K. Mellor, Mary Shelley: Her Life, Her Fiction, Her Monsters(1988)
- Marilyn Butler, Romantics, Rebels and Reactionaries(1981)
- Karen Valby, “Frankenstein and the Language of Monstrosity” (Modern Philology, 1990)
これらの研究では、フェミニズム、ポストコロニアリズム、生政治など、多様な視座から死と創造の問題が論じられています。
✅ ポイント:
- 難解な論文でも、冒頭と結論だけで全体像を掴むのが大切。
- 日本語研究と併せて読むことで、自分の立ち位置を国際的視野で調整できます。
5-5. 「理論枠組み」との接続性を評価する
文学研究では、「どのような視点から作品を読むか(理論的アプローチ)」がとても大事です。
📚 たとえば:
- 死生観に関連する理論:
- フーコー:生政治、生の管理
- アガンベン:ホモ・サケル、生の剥奪
- レヴィナス:他者の死に向き合う倫理
- 身体と人工生命の理論:
- ドナ・ハラウェイ『サイボーグ宣言』
- クレメンティーヌ・フーゲル『人造人間の倫理』
論文の中で、これらの理論に言及している文献は、あなたの議論を理論的に補強する「骨組み」となり得ます。
✅ この章のまとめ
| 観点 | 要点 |
|---|---|
| テーマの明確化 | 自分の問いと研究軸を持つことが文献評価の基準 |
| 文献の適否 | 主題・視点・理論・根拠が整っているかを確認 |
| 引用可能性 | 査読・出版社・脚注の有無で信頼度を判断 |
| 海外文献 | 全文読解でなく要点把握と併用でOK |
| 理論との接続 | 理論的視野がある文献は論文構築に有効 |
6. 実例で学ぶ!文献調査のステップバイステップ
「検索のやり方は分かったけれど、実際にどう進めたらいいか分からない…」
そんなあなたのために、実際のテーマを例にして、文献調査の具体的なステップを紹介します。
6-1. モデルテーマ:「『フランケンシュタイン』における死生観と倫理の表象」
今回取り上げるモデルテーマは以下のとおりです。
- ジャンル:イギリス文学(19世紀)
- 対象作品:メアリー・シェリー『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』
- 主題:死生観、生命倫理、創造行為、科学と道徳
6-2. 段階①|テーマをキーワードに分解する
まずは、テーマの要素を検索可能なキーワードに細分化します。
| 主題要素 | 検索語の例 |
|---|---|
| 作品名 | フランケンシュタイン、Frankenstein、Mary Shelley |
| 主題 | 死生観、生命倫理、倫理、科学と道徳、創造、再生 |
| 文学的観点 | 表象、ナラトロジー、ジェンダー、ロマン主義、象徴性 |
6-3. 段階②|複数のデータベースで検索する
▼ CiNii Research(日本語の先行研究)
- 検索例:「フランケンシュタイン AND 倫理」
- 結果例:
- 「『フランケンシュタイン』における生命倫理の葛藤」
- 「近代科学批判としてのメアリー・シェリー作品」
▼ Google Scholar(海外研究や英語文献)
- 検索例:
Frankenstein AND ethics AND death - 結果例:
- “Creating Life: Ethics and Responsibility in Frankenstein”
- “Romanticism and the Limits of Human Knowledge”
▼ NDL Online(書籍を探す)
- 検索例:「フランケンシュタイン 表象 死生観」
- 結果例:
- 『死と文学:西洋文学における死の表象』
- 『フランケンシュタインの時代と思想』
🔗 https://ndlonline.ndl.go.jp/
6-4. 段階③|集めた文献を分類・整理する
集めた文献を用途に応じて整理しておくと、後々の論文執筆が格段に楽になります。
| 分類 | 例 | 用途 |
|---|---|---|
| 直接的な先行研究 | 「フランケンシュタインにおける死と創造」 | 論の中心に引用 |
| 関連研究 | 「19世紀英国文学における科学と倫理」 | 理論的補強に使用 |
| 理論書・方法論 | フーコー『生政治の誕生』、ハラウェイ『サイボーグ宣言』 | 思想的枠組みとして使用 |
6-5. 段階④|書誌情報とメモをしっかり管理
- 書誌情報はZoteroやMendeleyで整理。
- メモには次のような内容を記載:
- 引用ページ
- 主要な論点(例:「創造行為と神の模倣との関係」)
- 批判的コメント(例:「作者の意図と読者の解釈にズレがある」)
6-6. 段階⑤|読解・再検索を繰り返す
- 1つの論文を読むことで、さらに調べるべきキーワードが見えてくる。
- 論文末尾の「参考文献」から、別の文献へと芋づる式にたどる。
- 疑問点は大学図書館のレファレンス・サービスに相談(非常に頼りになります!)
✅ この章のまとめ
- テーマを「検索語」に分解することがスタート地点
- データベースを横断して検索しよう(CiNii・Google Scholar・NDL Onlineなど)
- 検索結果は、使用目的別に分類・管理
- 調査は一度きりで終わらない。読む→メモ→調べ直すの繰り返しが力になる
このように、古典文学の研究でも現代的な検索手法が活用可能です。
『フランケンシュタイン』のような定番作品であっても、新しい視点や理論を用いることで独自の研究が可能になります。
7. よくある悩みとその対策:『フランケンシュタイン』研究のケースから
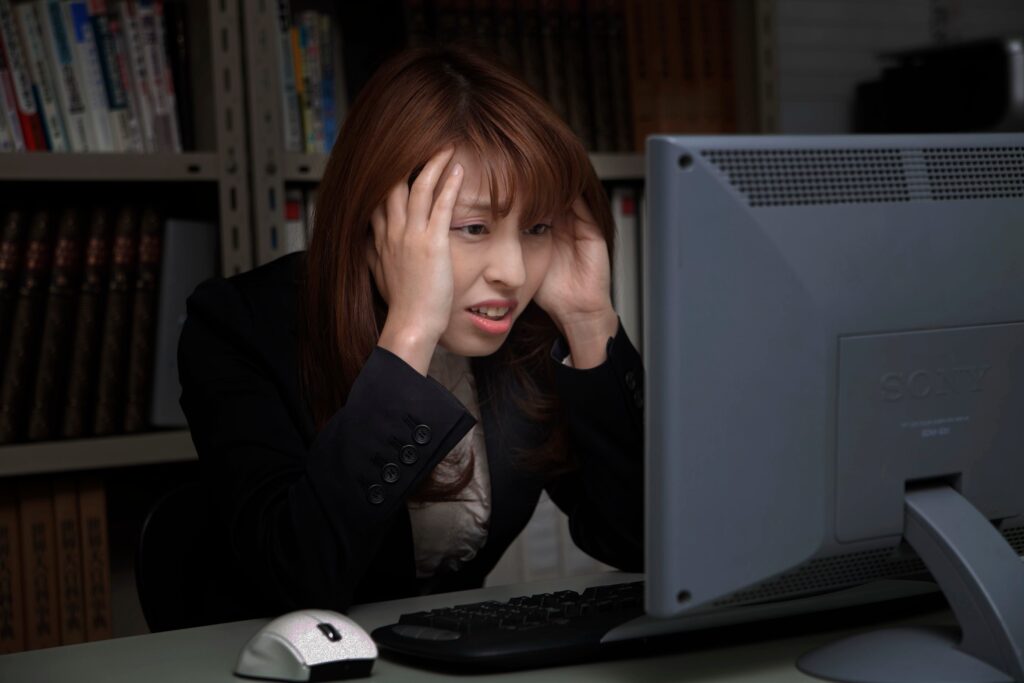
7-1. 「文献が多すぎて、何を読めばいいかわからない」問題
📌 よくある状況:
『フランケンシュタイン』は古典的な名作であり、研究書・論文が圧倒的に多い作品です。
Google ScholarやCiNiiで検索すると、何百件ものヒットが出て、途方に暮れてしまうことも。
✅ 対策:
- まずはレビュー論文や概観書を読む。
例:「『フランケンシュタイン』研究の展開」「ロマン主義文学と死生観」などの総説的な論文。 - 引用数の多い文献を優先する。
→ Google Scholarでは、引用数(Cited by ○○)が多い論文は影響力が高いと判断できる。 - 自分の主題に近い視点でフィルターをかける。
例:「倫理」や「ジェンダー」、「再生医療」「科学批判」などの絞り込み。
7-2. 「海外の論文をどう扱えばいいかわからない」問題
📌 よくある状況:
英語文献の中に、非常に有益そうな論文があるが、**読解に自信がない…**という不安。
✅ 対策:
- アブストラクト(要旨)と結論だけでも読む。
→ 論文の骨子が分かるだけで十分役立ちます。 - DeepLやGoogle翻訳を補助的に使う。
→ 機械翻訳でも、構造や主張はだいたい把握できる。 - 図書館の翻訳支援・文献取寄サービスを活用。
→ 国立国会図書館や大学図書館では、翻訳を頼むための資料整備がある場合も。
7-3. 「テーマが被っている研究がすでにあって落ち込む…」問題
📌 よくある状況:
「すでに『フランケンシュタイン』の倫理や死生観について論じた論文が存在している」
→「自分の研究に新しさがないのでは」と不安になる。
✅ 対策:
- 同じテーマでも、視点・問い・方法で差別化できる。
例:- 先行研究:「死を克服する科学への批判」
- あなたの研究:「死を受け入れることの倫理的価値」に焦点を移す
- 比較対象を工夫する。
→ 例:『ジキルとハイド』『アイランド』『バイオハザード』など、現代SF・ホラーとの比較によって独自性を出す。 - 理論枠組みを導入して視野を変える。
→ フーコー、ドナ・ハラウェイ、アガンベンなどの思想を組み込むことで、研究の位置づけを再構成できる。
7-4. 「構想段階で何をどこまで調べればいいの?」問題
📌 よくある状況:
まだ論文を書き出していない段階で、どの程度まで文献調査をするべきか分からない。
✅ 対策:
- 最初のステップは「仮説を立てる」こと。
→ 文献は仮説を補強したり、批判したりするために読む。 - 最初に10~20件の文献を読み、全体像をつかむ。
→ 全体像がつかめたら、自分の研究がそのどこに位置するかを考える。 - 論文執筆と並行して、検索・読解は続けていく。
→ 文献調査は一度で完了しません。**「調べながら書き、書きながら調べる」**スタイルが基本。
7-5. 「テーマが抽象的でうまく絞れない」問題
📌 よくある状況:
「死生観」「倫理」など、大きなテーマを扱う際、焦点がぼやけてしまう。
✅ 対策:
- 具体的なエピソードや登場人物から切り出す。
例:「クリーチャーが死を学習する場面」「ヴィクターが家族を失うことにどう向き合うか」 - 1つのキーワードに絞って先行研究を読む。
→ 例:「死を象徴する場面」や「創造者責任」だけに集中して数本の論文を精読。 - 本文に現れる表象の変化に注目する。
→ 作品中で「生命」や「死」がどのように描かれるかの変遷を追うことで、分析対象が明確になる。
✅ この章のまとめ
| 悩み | 対策のキーポイント |
| 文献が多すぎる | 絞り込み検索とレビュー文献の活用 |
| 海外文献が不安 | 要旨と結論を読み、翻訳支援を活用 |
| 既存研究と被る | 視点・方法・比較対象で差別化 |
| どこまで調べるか | 最初は10~20件+並行調査 |
| テーマが抽象的 | 登場人物・エピソードから具体化 |
このように、『フランケンシュタイン』のような研究が盛んな作品でも、文献調査の工夫によって独自の問いを立てることは十分可能です。
迷ったときは、「誰が」「どんな問いで」「どんな方法で」論じているかを見極めましょう。
8. まとめ:文献調査力は研究者としての基礎体力である
8-1. 文献調査とは、研究の“目”を鍛えること
研究における文献調査とは、ただ資料を探して並べる作業ではありません。
それは次のような力を鍛えるトレーニングです:
- 問いを立てる力(どんな視点で読み解くか)
- 先行研究を位置づける力(自分の研究の位置を知る)
- 批判的に読む力(鵜呑みにせず、比較し、検証する)
研究のクオリティは、テーマ設定でも、文章表現でもなく、「調べ方」そのものに宿るのです。
8-2. 文献調査の力は書く前に身につけよ
論文を書き出してから、「あれも調べておけばよかった」「この主張の根拠が薄い」と後悔するケースは少なくありません。
構想段階から文献調査に時間をかけることで、以下のような恩恵があります:
- 主張に裏づけが出せる
- 研究の独自性を検証できる
- 「書くべきこと/書かなくてもよいこと」が明確になる
8-3. あなたの研究は、すでに学術の“対話”の中にある
卒論であれ博論であれ、私たちが行う研究は、これまでの無数の研究者との対話の延長線上にあります。
文献調査とは、そうした対話を聞き取り、自分の言葉で返答を試みる知的コミュニケーションの訓練でもあります。
- あなたの問いは、誰かの問いとどこが違うか
- あなたの視点は、過去の議論にどう応答するか
それを明確にすることで、あなたの研究は、ただの感想から「学術」へと変貌していくのです。
終章:参考文献とおすすめリンク集
📚 入門書・ハンドブック(日本語)
| タイトル | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|
| 『論文の教室』 | 戸田山和久 | NHK出版新書 |
| 『大学生のためのレポート・論文術』 | 小笠原喜康 | 講談社現代新書 |
| 『人文学と情報』 | 小風尚樹 編 | 放送大学出版会 |
| 『情報探索術』 | 大谷卓史 他 | 勁草書房 |
🧰 ツール・サービス
| サービス名 | URL | 概要 |
|---|---|---|
| CiNii Research | https://cir.nii.ac.jp/ | 日本の学術論文を検索できる最大級のデータベース |
| Google Scholar | https://scholar.google.com/ | 国内外の論文を横断的に検索できる |
| 国立国会図書館(NDL Online) | https://ndlonline.ndl.go.jp/ | 全国の出版物・所蔵を検索し、複写申請も可能 |
| J-STAGE | https://www.jstage.jst.go.jp/ | 日本の学協会が発行する学術雑誌の多くを無料公開 |
| IRDB(機関リポジトリ) | https://irdb.nii.ac.jp/ | 全国の大学リポジトリにある論文・紀要を検索可能 |
| Zotero | https://www.zotero.org/ | 文献管理と引用ができる無料ツール |
✅ この記事を終えて:あなた自身の「知の地図」を描こう

研究の旅において、文献調査は地図を描く作業です。
道に迷ったとき、先人の軌跡があなたを導いてくれるでしょう。
しかし、最終的に歩むべきルートは、あなたが自分の問いと格闘しながら切り拓くものです。
どうかこの記事が、あなたの研究の旅にとって、信頼できるコンパスとなりますように。
ご覧いただき、ありがとうございました!
もしこのガイドが役立ったと感じたら、ぜひシェア・ブックマークをお願いします📘✨