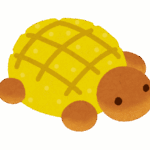1. はじめに:卒論とは何か?
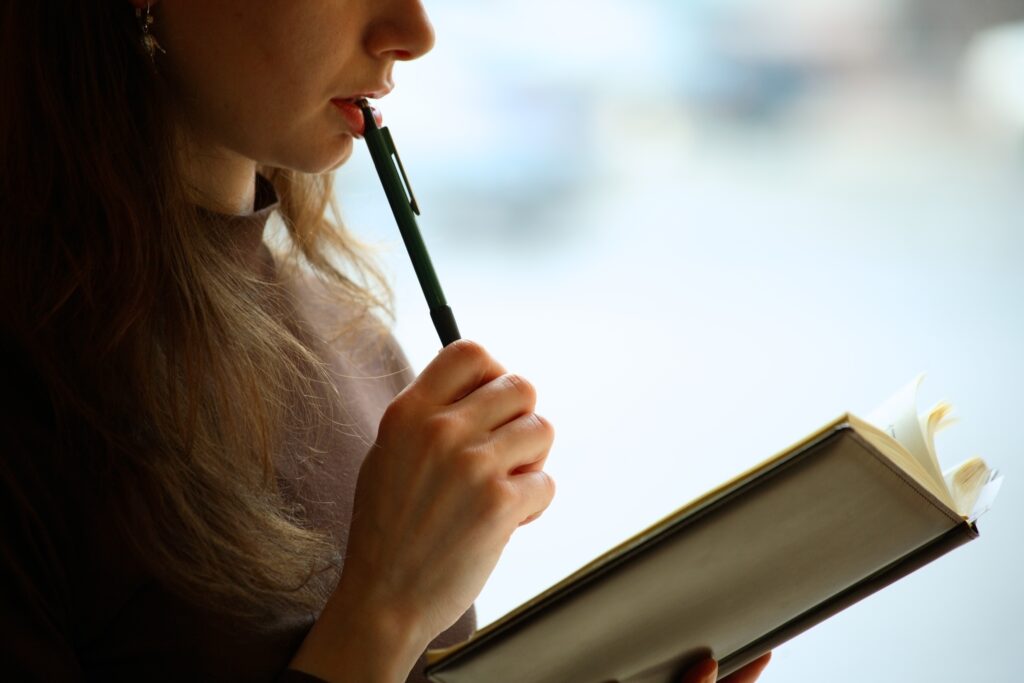
卒業論文(以下、卒論)は、大学での学びの集大成とも言える重要な課題です。単なるレポートではなく、自ら問いを立てて、資料や文献をもとに論理的に考察する「学術的な論文」として書く必要があります。
卒論を通じて問われるのは、「どれだけ知っているか」よりも、「どのように考え、表現できるか」です。卒論は、知識や理解を土台にして、自分自身の視点で世界を見る訓練でもあります。
2. テーマの選び方と問いの立て方
2-1. 興味関心からテーマを見つけよう
まずは、自分が**「本気で向き合える問い」**を探しましょう。
- 大学生活で印象に残った授業や本は?
- 何度も考えたことのある問題は?
- 他人と議論してみたくなる話題は?
例:「ジブリ作品における自然観」「戦争文学における『罪』の描かれ方」など。
2-2. テーマから「問い」へと掘り下げる
卒論の中心は「問い」です。問いがあることで、論文は単なる紹介ではなく、考察と主張が可能になります。
- ❌ テーマだけ:「夏目漱石について」
- ✅ 問い:「夏目漱石は『こころ』で近代的自我をどのように描いているか?」
2-3. 良い問いの3つの条件
- 明確である(何について、何を問うかがはっきりしている)
- 答える意義がある(誰かが読む意味のある問いになっている)
- 文献や資料で答えられる(検証可能な問いである)
3. 先行研究の探し方と読み方
3-1. なぜ先行研究が重要か?
卒論は「自分の考え」だけで完結してはいけません。先人の研究(=先行研究)を参照し、対話しながら書くことが求められます。
- すでに誰かが論じたことと、どう違うのか?
- 自分の主張はどの位置にあるのか?
を明示することで、論文としての信頼性と独自性が生まれます。
3-2. 文献の探し方:まずは大学図書館とCiNiiから
- **大学図書館の蔵書検索システム(OPAC)**を活用
- **CiNii Research(https://ci.nii.ac.jp/)**で論文検索
- **Google Scholar(https://scholar.google.com)**でも検索可能
キーワードで検索し、タイトルと要旨を読んで取捨選択しましょう。
3-3. 先行研究の読み方のコツ
- 主張は何か?
- 使っている資料・理論は何か?
- 自分の研究とどう関係するか?
をメモしながら読むと、自分の論にどう活かせるかが見えてきます。
4. 構成の立て方と論の展開

4-1. 卒論の基本構成:5つの柱
- 序論:問いの提示、背景、研究目的、構成の予告
- 本論①:理論・背景整理
- 本論②:分析・考察
- 本論③:補強・反論への対応
- 結論:問いへの答え、全体のまとめ、展望
4-2. 論の流れは「因→果」で書く
- ❌「Aは素晴らしい。なぜなら…」
- ✅「Bという理由があるため、Aは素晴らしいと考えられる」
「事実→分析→結論」の順で論理を展開しましょう。
4-3. 構成づくりのヒント:仮目次を作る
章ごとのタイトルと要点を書き出してみましょう:
markdown
コピーする編集する
1. 序論:問いの背景と目的
2. 理論と文献の整理
3. ○○の分析
4. 他解釈との比較
5. 結論と今後の課題
5. 文章表現と執筆の注意点
5-1. 論理的で明快な文章を意識する
- 一文を短く(60字以内推奨)
- 主語と述語を対応させる
- 接続詞で論理をつなぐ
5-2. 客観的・丁寧な文体を使う
- ❌「すごく面白い」
- ✅「読者の関心を引きつける構造を有する」
基本は「〜である」調で統一しましょう。
5-3. 引用・注記のルールを守る
- 直接引用:「……」(出典)
- 間接引用:〜と〇〇は述べている(出典)
剽窃にならないよう、必ず出典を明記!
5-4. アウトラインを作ってから書く
書きながら考えるのではなく、書く前に構成を固めておくと、迷わずに進めます。
6. 推敲とフィードバックの活用
6-1. 推敲の3ステップ
- 構造の見直し:章立て、論理の順番
- 主張の深掘り:繰り返しの削除、根拠の追加
- 表現の確認:誤字脱字、接続詞、敬体/常体の統一
6-2. 他者の目を借りる
- 指導教員に早めに相談
- ゼミ仲間と見せ合う
- 家族や友人に説明してみる
6-3. 最終チェックリスト
✅ 表紙・目次・ページ番号の整備
✅ 引用・参考文献の記載漏れなし
✅ 誤字脱字チェック済み
✅ 指導教員の指示を満たしている
7. よくある悩みとその解決法

Q1:テーマが広すぎる?
→ 興味のある視点から「問い」を絞り込もう
Q2:文献が多すぎる?
→ まず基本文献や重要論文に的を絞る
Q3:論がぶれる?
→ 常に構成表を見ながら書く
Q4:やる気が続かない?
→ 毎日のスモールゴールを設定
Q5:内容に自信が持てない?
→ 自分で考えたプロセスこそが卒論の価値!
まとめ:卒論は「問いを通じて成長する旅」

卒論を書くという経験は、自分の問いを言葉で形にしていく、貴重な知的プロセスです。うまくいかない日もあるでしょう。でも、悩みながら、試行錯誤しながら書いた論文は、**その人だけの「知の記録」**になります。
あなたの卒論が、実りあるものになることを心から願っています!