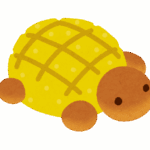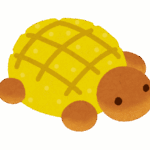こんにちは。いま、博士課程への進学を控えている文学専攻の先輩です。
この文章は、「学部で文学を学んできて、卒業後の進路として修士課程に進むか、それとも就職するかで迷っている」あなたに向けて書いています。
私自身、修士に進学するかどうか、長く悩みました。
文学で生きていくって、どういうことなんだろう。
この道を選んで本当に大丈夫なんだろうか。
社会に出る勇気がないから逃げてるだけなんじゃないか……?
そんな不安を乗り越えながら、今も文学に関わる道を歩いています。
ここでは、「文学を学ぶことに価値があると信じてきたあなた」に向けて、できる限り率直に、修士課程で何が得られるのか、何が大変なのか、どんな未来があるのかを綴っていきます。
第1章:なぜ進学を迷うのか──文学と現実のギャップ
「文学が好き」だけでは足りない?
おそらく、あなたは文学が好きで、大学でも何年もかけて小説・詩・戯曲・批評・思想書などを読んできたことでしょう。
作品世界に浸ることも、考察を深めることも、言葉で表現することも楽しい。
でも、ふと我に返ると、こう思うことはありませんか?
- 「このまま文学を学び続けて、将来どうするんだろう?」
- 「研究職になれるのはほんの一握りって聞くけど……」
- 「学問の世界は閉じていて、社会で通用しないんじゃないか?」
これらの不安は、ごく自然なものです。
なぜなら、文学の価値は数字では測れないからです。
工学や医学、法学などの「資格」や「技術」が目に見える形で評価されやすい一方、文学の知は、抽象的で、役に立つのかどうかもわかりにくい。
でも、だからこそ「問う力」「読み解く力」「言葉で表現する力」が、今の社会においてかえって重要になってきているのだと、私は信じています。
第2章:「文学を学ぶ」とは何か──修士課程の学びの実感
学部との違い
修士課程に進むと、文学の学びは一気に「自分の問いに責任を持つもの」へと変わります。
- なぜこの作品を取り上げるのか
- どのような理論や視点で読み解くのか
- 過去の研究とどう関係づけるのか
これは、単なる「読書感想文」や「作品解説」ではありません。
自分の視点で文学を読み、それを論文という形で表現し、学会で発表し、批評にさらされながら言葉を研ぎ澄ませていく──そのプロセスは、厳しくも刺激的です。
自分の「問い」を持つことの意味
私が修士に進学して実感したのは、**「文学の問いは、結局、自分自身の問いでもある」**ということです。
- なぜこの作家に惹かれるのか?
- なぜこの作品のこの場面が、どうしても引っかかるのか?
- 自分が生きてきた文脈と、作品の中の言葉は、どう響き合っているのか?
文学を研究することは、自分を探すことでもあります。
その旅に本気で取り組めるのが、修士の2年間です。
第3章:修士課程の現実──孤独と自由、そして成長
「自由すぎる」苦しさ
修士課程の生活は、とても自由です。
授業は週に数回、あとは自分の研究に時間を使えます。
でも、この「自由」は時に孤独です。
「何をしたらいいか分からない」「誰も評価してくれない」「成果が出ない」──そう感じることもあります。
だけど、この時間をどう使うかは、すべて自分に委ねられています。
たくさん本を読む、古書店や図書館を歩き回る、言葉を練る──その全てが研究の一部です。
仲間と指導教員の存在
修士生活を支えてくれるのが、指導教員との関係と同じ専攻の仲間たちです。
- 論文のアイデアにフィードバックをくれる先生
- 夜遅くまで作品について語り合える友人
- 自分と違う視点を持つ研究者との出会い
こうした人間関係が、あなたの文学の世界を広げてくれます。
文学は一人で読むものだけど、研究は一人では深められないものだと気づくはずです。
第4章:文学とキャリア──修士を出たらどうなるのか?
研究職への道
正直に言えば、文学の研究職は狭き門です。
修士課程を出たあとに博士課程に進み、論文を書き、学会で認められ、ようやく専任職にたどり着けるかどうかという厳しさがあります。
でも、それを「だから無理」とあきらめるのではなく、むしろ**「だからこそ、自分はなぜ文学をやるのか」を問う覚悟を持てるか**が大切です。
文学と社会の接点
一方で、文学修士の学びは、研究職以外にも活かせる力を育ててくれます。
- 言葉を丁寧に読み、解釈し、伝える力
- 多様な価値観に対して柔軟に思考できる力
- 問いを立てて、論理的に展開する力
これらは、出版・編集・教育・文化事業・行政・NPOなど、多くの現場で必要とされています。
就職活動では、「文学で何を考え、何を得たのか」を自分の言葉で語れることが、最大の強みになります。
第5章:お金の話をしよう──経済的不安とその対策
文学研究は、心を豊かにするものです。
でも、それだけでは食べていけません。
だからこそ、経済的な支援制度を調べて活用することがとても大切です。
- 日本学生支援機構の第一種(無利子)・第二種(有利子)奨学金
- 授業料免除制度(大学によって異なる)
- TA(授業補助)のアルバイト
- 民間財団の給付型奨学金(例:吉田育英会、ロータリー財団など)
- 各大学独自の支援制度(入試成績上位者対象の免除など)
進学を決める前に、志望校の事務や指導教員に相談し、どんな支援があるかを具体的に把握しましょう。
第6章:「進むか、進まないか」を決める5つの問い
- あなたが研究したい作家・作品・テーマは何か?
- なぜ、その対象に惹かれるのか?個人的な動機は?
- それを2年間かけて向き合い続けられる情熱があるか?
- 研究を通して、あなたはどんな言葉を社会に届けたいのか?
- 経済的・心理的に支えてくれる環境があるか?
これらの問いに対して、すぐに答えが出なくてもかまいません。
でも、一つひとつ考えていくことで、あなたなりの選択の軸が見えてくるはずです。
終章:「文学を学びたい」と思った気持ちを、大切に
最後に、どうしても伝えたいことがあります。
それは──「文学を学びたい」と思ったあなたの気持ちは、間違っていないということ。
社会に出てからのほうが、文学の意味が身にしみる瞬間は多いです。
人とすれ違う痛み、孤独、迷い、そして希望──
それらを、私たちは文学の中ですでに知っている。
だからこそ、「文学を通して世界と関わり続けたい」と願うあなたの選択は、たとえ遠回りに見えても、豊かな時間となるはずです。
どんな道を選んでも、文学で鍛えた眼差しとことばは、きっとあなたの支えになります。
迷った分だけ、強くなれる。
どうか、あなたの問いを、あなた自身の言葉で、これからも紡いでいってください。